自滅への道を突き進む神社本庁田中体制
-参院選敗北で石破降ろしが吹き荒れる自民党の内実
(月刊「レコンキスタ」令和7年8月1日号)
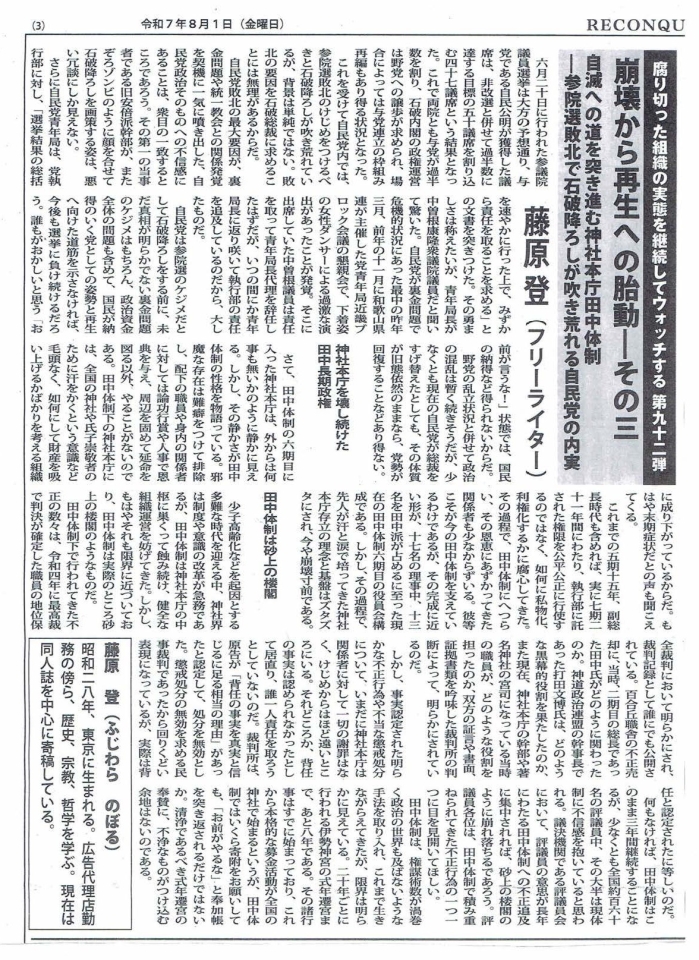
〇神社本庁を壊し続けた田中長期政権
さて、田中体制の六期目に入った神社本庁は、外からは何事も無いかのように静かに見える。しかし、その静かさが田中体制の性格を物語っている。邪魔な存在は難癖をつけて排除し、配下の職位や身内の関係者に対しては論功行賞や人事で恩典を与え、周辺を固めて延命を図る以外、やることがないのである。田中体制下の神社本庁には、全国の神社や氏子崇敬者のために汗をかくという意識など毛頭なく、如何にして財産を吸い上げるかばかりを考える組織に成り下がっているからだ。もはや末期症状だとの声も聞こえてくる。
これまでの5期15年、副総長時代も含めれば実に7期21年間にわたり、執行部に託された権限を公平公正に行使するのではなく、いかに私物化、利権化するかに腐心してきた。その過程で、田中体制にへつらい、その恩恵にあずかってきた関係者も少なからずいる。彼等こそが今の田中体制を支えているわけであるが、その完成に近い形が、17名の理事中、13名を田中派が占めるに至った現在の田中体制6期目の役員会構成である。しかし、その過程で、先人が汗と涙で培ってきた神社本庁存立の理念と基盤はズタズタにされ、今や崩壊寸前である。
〇田中体制は砂上の楼閣
少子高齢化などを起因とする多難な時代を迎える中、神社界は制度や意識の改革が急務であるが、田中体制は神社本庁の中枢に巣くって蝕み続け、健全な組織運営を妨げてきた。しかし、もはやそれも限界に近付いており、田中体制は実際のところ砂上の楼閣のようなものだ。
田中体制下で行われてきた不正の数々は、令和4年に最高裁で判決が確定した職員の地位保全裁判において明らかにされ、裁判記録として誰にでも公開されている。百合丘職舎の不正売却に、当時、2期目の総長であった田中氏がどのようにかかわったのか。神道政治連盟の幹事長であった打田文博氏は、どのような黒幕的役割を果たしたのか、また現在、神社本庁の幹部や著名神社の宮司になっている当時の職員が、どのような役割を担ったのか、双方の証言や書面、証拠書類を吟味した裁判所の判断によって、明らかにされているのだ。
しかし、事実認定された明らかな不正行為や不当な懲戒処分について、いまだに神社本庁は関係者に対し手一切の所在はなく、けじめからはほど遠いところにいる。それどころか、背任の事実は認められなかったとして居直り、誰一人責任を取ろうとしていないのだ。裁判所は、原告が「背任の事実を真実と信じるに足る相当の理由」があったと認定して、処分を無効とした。懲戒処分の無効を求める民事裁判であったから回りくどい表現になっているが、実際は背任と認定されたに等しいのだ。
何もなければ、田中体制はこのまま3年間継続することにあるが、少なくとも全国約160名の評議員中、その大半は現体制に不信感を抱いていると思われる。議決機関である評議員会において、評議員の意思が長年にわたる田中体制への不正追及に集中されれば、砂上の楼閣のように崩れ落ちるであろう。評議員各位は、田中体制で積み重ねられてきた不正行為のひとつひとつに目を見開いほしい。
田中体制は、権謀術数が渦巻く政治の世界も及ばないような手法を取り入れ、これまで生きながらえてきたが、限界は明らかに見えている。20年ごとに行われる伊勢神宮の式年遷宮まで、あと8年である。その諸行事はすでに始まっており、これから本格的な募金活動が全国の神社で始まるというが、田中体制ではいくら寄付をお願いしても、「お前がやるな」と奉加帳を突き返されるだけではないか。清浄であるべき式年遷宮の奉賛に、不浄なものがつけ込む余地はないのである。